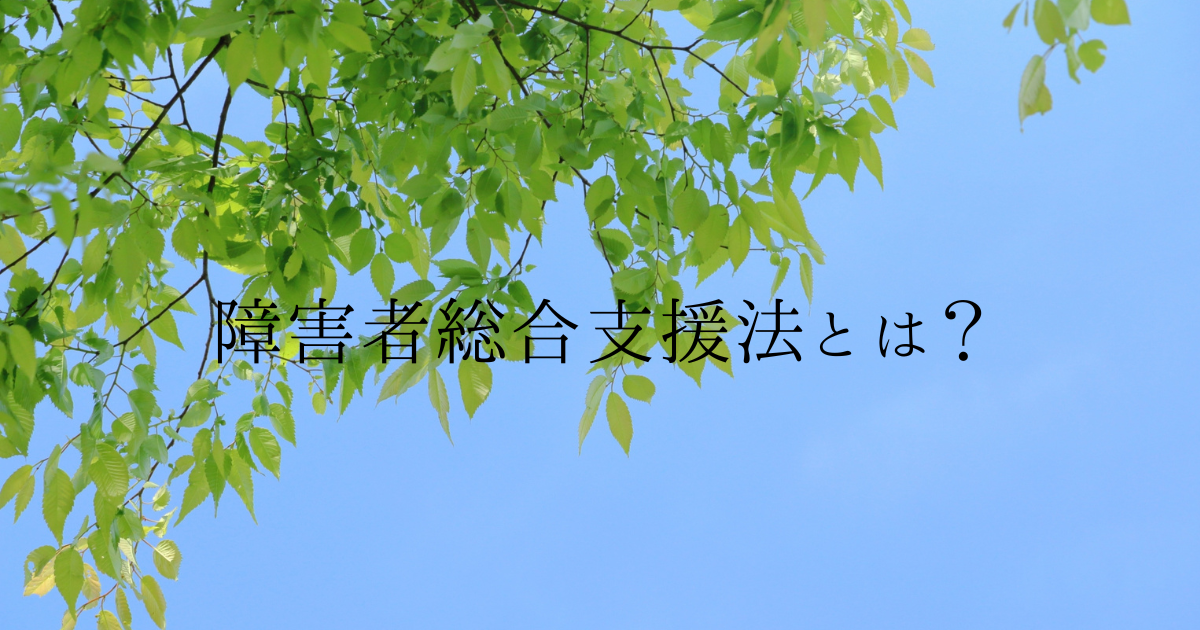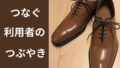障害のある人が自立した生活を送るために、どのような支援を受けられるのかをご存じですか?日本では、「障害者総合支援法」という法律のもと、障害のある方が安心して暮らせるように、さまざまなサービスが提供されています。今回は、障害者総合支援法の概要や対象者、具体的な支援内容について詳しく解説します。
- 障害者総合支援法とは?
障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)は、障害のある人が日常生活や社会生活を円滑に送れるよう、必要な支援を提供することを目的とした法律です。2013年に「障害者自立支援法」を改正する形で施行され、従来よりも幅広い障害に対応し、地域社会での共生を推進するための仕組みが整えられました。
- 対象となる人
障害者総合支援法では、以下のような障害を持つ方が対象となります。
- ・身体障害(視覚・聴覚・肢体不自由など)
- ・知的障害(知的発達の遅れによる生活支障)
- ・精神障害(統合失調症、うつ病、発達障害など)
- ・難病患者(パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)など)
特に、難病患者も対象に含まれたことで、これまで福祉制度の支援を受けにくかった人たちにも必要なサービスが提供されるようになりました。
- 受けられる支援の種類
障害者総合支援法では、以下のような支援が受けられます。
① 介護給付(生活を支えるサービス)
- ・居宅介護(ホームヘルプ):自宅での入浴・排せつ・食事などの支援
- ・重度訪問介護:重度の障害者向けの24時間介護支援
- ・同行援護:視覚障害者の外出時の移動支援
- ・短期入所(ショートステイ):一時的に施設での介護を受けられる
- ・施設入所支援:施設に入所して介護を受ける
② 訓練等給付(自立や就労を支えるサービス)
- ・自立訓練(機能訓練・生活訓練):日常生活の動作訓練
- ・就労移行支援:企業への就職を目指すための訓練・サポート
- ・就労継続支援(A型・B型)
- A型:雇用契約を結び、最低賃金が適用される
- B型:雇用契約なしで軽作業を行う
③ 地域生活支援(地域での暮らしを支えるサービス)
- ・移動支援:外出が困難な障害者の移動をサポート
- ・意思疎通支援:手話通訳者や要約筆記者の派遣
- ・日中一時支援:家族の負担を軽減するための一時預かり
- 障害支援区分とは?
支援が必要な度合いを判定するために「障害支援区分」という仕組みがあります。市町村が審査会を設置し、障害の程度や日常生活の困難さに応じて区分を決定します。
- ・区分1~2:軽度の支援が必要
- ・区分3~4:中程度の支援が必要
- ・区分5~6:重度の支援が必要
支援区分によって、受けられるサービスの種類や量が変わります。
支援が必要な方は、まず市区町村の窓口で相談してみるのが良いでしょう。
- 相談支援の仕組み
障害のある人が適切なサービスを受けられるよう、市町村には「相談支援専門員」が配置されています。
- ・サービス等利用計画の作成:適切なサービスを受けるための計画書を作成
- ・地域移行支援:施設や病院から地域での生活へ移るための支援
- ・地域定着支援:単身生活をする障害者が安心して暮らせるよう支援
- 費用負担の仕組み
サービスを利用する際の費用は、所得に応じて負担額が異なります。
世帯の所得区分 負担上限額
生活保護世帯・低所得(市町村民税非課税) 0円
一般(所得割16万円未満) 9,300円
一般(所得割16万円以上) 37,200円
低所得者ほど負担が軽減される仕組みになっています。
- まとめ
障害者総合支援法は、障害のある人が「住み慣れた地域で、自分らしく暮らせる」ことを基本理念とし、包括的な支援を提供する法律です。
この法律によって、障害のある方が日常生活や社会生活で必要なサポートを受けやすくなり、より自立した生活を目指せるようになっています。
自分や家族がどのような支援を受けられるのかを知り、必要なサービスを活用していきましょう。
就労継続支援B型つなぐ
所在地:福岡市早良区原6-23-18
電話番号:092-852-9910
営業時間:9:00~17:00
定休日:日祝