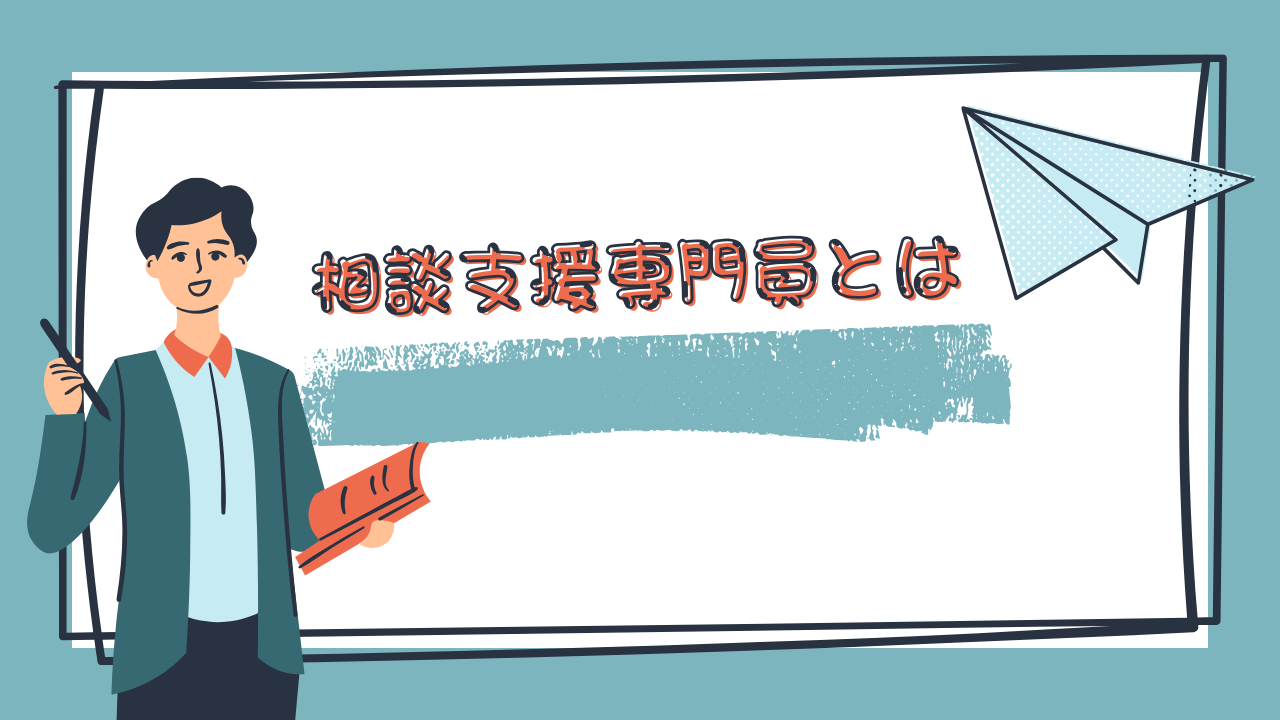私が就労継続支援B型事業所に通うまでにも、たくさんの方々にお世話になりました。
その中で今もB型事業所と密接な関りがあり、定期的に面談してお世話になっているのは、「相談支援専門員」の方です。
そこで、今回は、「相談支援専門員」という職業について調べてみました。
相談支援専門員は数ある障害者支援の仕事の中でも、比較的新しい職業です。
相談支援専門員の役割は、障害児・障害者の意向を踏まえて、自立した日常生活や社会生活の実現のため、支援・中立・公平な立場から障害福祉サービス利用のための支援などを行います。
具体的には、「生活全般にかかわる相談・情報提供やサービスなど利用計画の作成、モニタリング、関係機関との連絡・調整などの業務」を担います。
それでは、相談支援専門員は、支援を必要とする、障害のある利用者やその家族らにどのような働きかけをしているのか、また、以下にまとめました。
相談支援専門員の役割
相談支援専門員は、障害のある人が地域社会で生活を送る上での困りごとや悩みを解決するために、必要な支援をつなぐ重要な役割を担っています。
具体的には、利用者がスムーズに福祉サービスを受けられるように、豊富な知識と情報収集力を駆使して、福祉や支援を提供します。
また、相談支援専門員は、「サービス等利用計画」を作成し、それを市区町村に提出します。
この計画がなければ、福祉サービスを受けることができないため、非常に重要な役割を果たします。
サービス等利用計画の作成
サービス等利用計画は、障害福祉サービスを受けるために必要不可欠な書類です。
相談支援専門員は、利用者のニーズに合った計画を立て、市区町村に提出します。
計画には、利用者がどのような福祉サービスを必要としているか、どのように生活を改善していくかを明確に記載します。
サービス等利用計画を作成した後も、利用者の困りごとが解消されているか、新たに問題が発生していないかを定期的に確認します。
これにより、継続的に利用者の状況に合わせたサポートが提供されることになります。
相談支援専門員になるには?
相談支援専門員になるためには、一定の実務経験と専門的な研修が必要です。
具体的には、以下の3つのルートで相談支援専門員になることができます。
A.相談支援業務ルート
障害者支援に従事した経験が5年以上ある場合、このルートを通じて相談支援専門員になることができます。
具体的には、障害児相談支援事業や知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センターなどで相談業務を行った経験が該当します。
また、医療機関で相談支援業務に従事していた場合でも認められることがあります。
B.介護業務ルート
介護業務に5年から10年以上従事した経験がある方は、このルートを通じて相談支援専門員になることができます。
施設や医療機関で介護業務を行っていた場合に認められます。
また、介護に関する資格を持っていると、5年の実務経験で認められることがあります。
C.国家資格ルート
医師や看護師、社会福祉士などの国家資格を5年以上保持している場合、このルートを通じて相談支援専門員の資格を取得できます。
さらに、AまたはBのルートを通じて3年以上の相談支援業務または介護業務の経験を積むことが求められます。
相談支援専門員に必要な研修
相談支援専門員になるためには、必要な実務経験を満たした後、研修を受けることが求められます。
この研修は、障害福祉全般についての専門知識や支援技術を学ぶ重要な時間です。
研修では、以下のような内容を学びます。
- 相談支援(ケアマネジメント)の基本的な考え方
- 利用者のニーズに合ったサービス等利用計画の作成方法
- 権利擁護と虐待防止について
- 関係機関との協力方法やファシリテーション技術
- 地域自立支援協議会についての理解
この研修は、通常5日間程度で行われ、年に1〜3回、都道府県ごとに実施されます。
全課程を修了することで研修が認められ、資格取得に必要なステップを踏むことができます。
資格の更新について
相談支援専門員の資格は取得後も更新が必要です。
更新は5年に1度行われ、更新には「相談支援現任研修」を受けることが求められます。
この研修を受けることで、最新の知識と技術を習得し、専門的なサポートを継続して提供できるようになります。
まとめ
相談支援専門員は、障害のある人が地域社会で自立し、生活を豊かにするために必要な福祉サービスを提供する重要な役割を担っています。
相談支援専門員になるためには、一定の実務経験と専門研修を受ける必要があり、資格の更新も必要です。
地域で暮らす障害者の方々にとって、相談支援専門員は欠かせない存在であり、その活動は非常に意義深いものです。
障害福祉の分野に興味がある方、または支援の現場で活躍したいと考えている方にとって、非常に興味深い職業ではないでしょうか。
814-0022
福岡県福岡市早良区原6丁目23番18号
電話番号:092-852-9910
受付時間:平日9:00~17:00
土 9:00~14:00