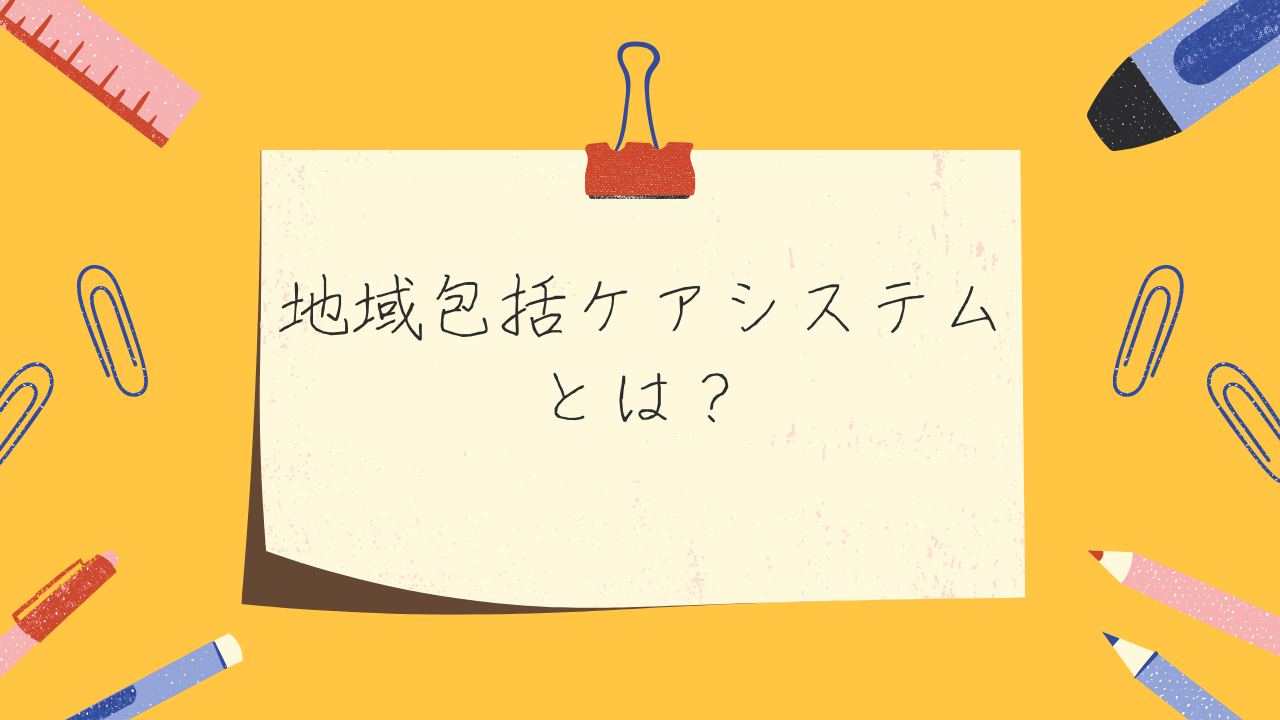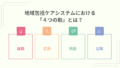2025年、日本はかつてない超高齢化社会を迎えます。
1947年~1949年に生まれた「団塊の世代」がすべて75歳以上の後期高齢者となる年が、まさにそのタイミングです。
高齢者が安心して暮らせる社会をどう作っていくのか、その答えの一つとして国が整備を進めているのが、「地域包括ケアシステム」です。
地域包括ケアシステムとは?
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者などが住み慣れた地域で自分らしく、安心して暮らし続けるために必要な支援を、地域で一体的に提供する仕組みのことです。
具体的には、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」という5つの要素を、地域単位(おおよそ30分圏内)で一体的に提供できる体制の整備が求められています。
病院や施設に頼るだけでなく、地域に根ざしたサービスの中で高齢者ができる限り自立した生活を送れるようにすることが、この仕組みの大きな目的です。
なぜ今、地域包括ケアシステムなのか?
日本の急速な少子高齢化により、高齢者人口は年々増加。一方で生産年齢人口は減少し、介護や医療を担う人材不足が深刻化しています。
2000年に介護保険制度がスタートして以降、介護を必要とする高齢者の数は右肩上がりに増加し続けてきました。
2025年には、約800万人の団塊の世代が後期高齢者となり、医療・介護の需要がピークを迎えるとされています。
こうした背景から、病院や介護施設だけでの対応には限界があるとして、地域全体で支える仕組みの必要性が求められています。
制度としての進化と整備の歩み
地域包括ケアシステムという言葉が初めて登場したのは、2005年の介護保険法改正時です。
以降、地域包括支援センターの創設を皮切りに、在宅医療と介護の連携、地域ケア会議の推進、介護予防・日常生活支援総合事業の導入などが行われ、体制強化が進められてきました。
2012年の法改正では、自治体がこのシステムを推進する義務を担うことが明文化され、2015年にはさらに実践的な取り組みが導入されました。
国を挙げての支援体制が整ってきた今、地域に根差した取り組みがますます重要になっています。
地域の「助け合い」が重要
地域包括ケアシステムを機能させるためには、制度やサービスだけでなく、「人と人とのつながり」が不可欠です。
高齢者が必要なときに医療・介護サービスを受けられる体制に加え、普段から顔の見える関係を築くことで、孤立や緊急時のリスクを軽減することができます。
地域で支え合いながら、必要なときに手を差し伸べられるような、「共生社会」の実現こそがこれからの高齢化社会に求められていると言えるのではないでしょうか。
まとめ
地域包括ケアシステムは、単なる制度ではなく、人々の暮らしを守るための新しいライフスタイルの提案でもあります。
高齢者が最期までより良い生活を送るために、地域全体で支え合う仕組みをどう整えていくかは、私たちにも関わる重要な課題です。
2025年を目前に控えた今、自分の地域でどのような取り組みが進んでいるのかを知り、できることから参加していくことが豊かな超高齢社会への第一歩かもしれません。
814-0022
福岡県福岡市早良区原6丁目23番18号
電話番号:092-852-9910
受付時間:平日9:00~17:00
土 9:00~14:00